大分県 消費生活・男女共同参画プラザの主催にて
平成25年度「働く女性のためのステップアップ講座」3回シリーズの
講師として深月敬子が担当させていただきました。
ディスカッション、事例ワークなど演習を多く含んだ実践的な講座となりました。
女性同士のつながり、助け合い、信頼関係がとても大事・・・という言葉が飛び交っていました。
皆さんのご参加ありがとうございました。

先日行われたY社様、全九州から集まったのは100名を超す事務担当社員の皆様です。
北部九州と南部九州の2地区に分かれて、1日研修が開催されました。
各支店から事務を担当する社員の皆さん、一堂に集まりました。
グループに分かれた実習やロールプレイを交えて楽しく、そして厳しい1日でした。
当社の講師は安岡文代講師、そして木村千歳講師の2名が担当しました。
皆さん、とても真剣で熱心です。そして素直で、すぐに行動に移していただいています。
研修後には、
・これからもっと、お客様を気持ちよくおもてなししたい
・商品だけでなく私達の笑顔や心づかいでお客様をファンにしたい
・日ごろの電話応対や来客応対に、いいかげんな点や雑な点が多かったことを反省して
たくさん改善すべきことがわかって良かった
などの感想をいただきました。
拠点にもどって、皆さんが他の社員をリードしておもてなし文化を根付かせていただきたいと
願っております。
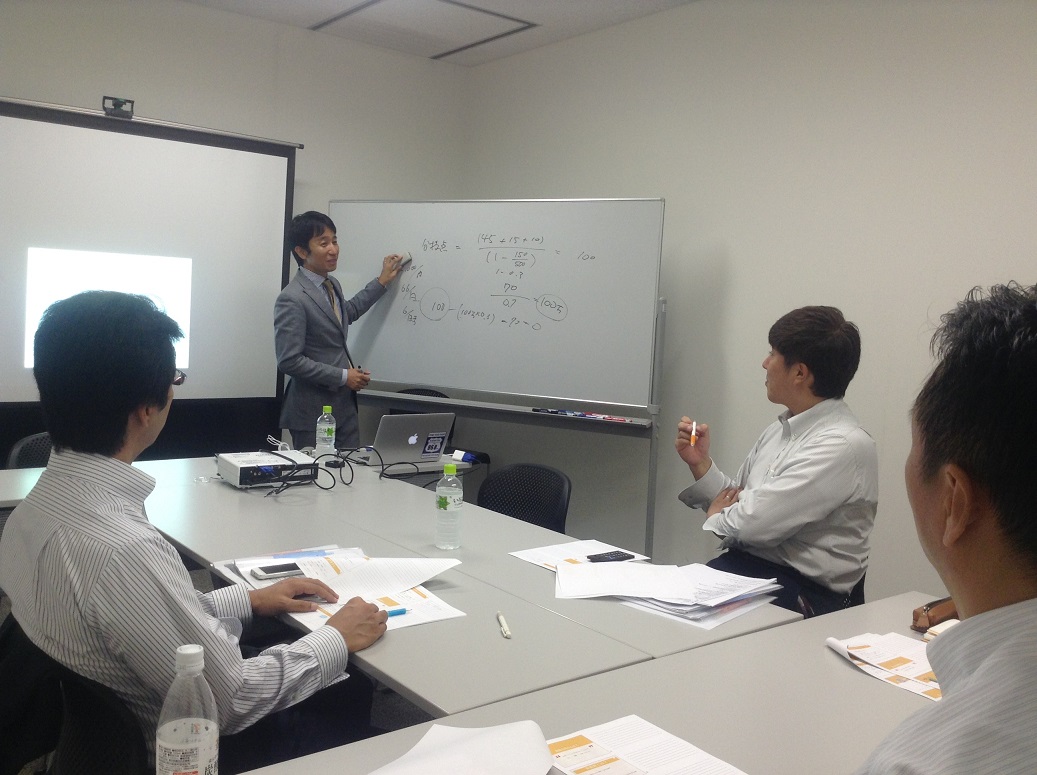
8月開講の経営幹部養成講座も6回講座の中間となりました。
今回は経営数字をテーマとして学習しました。
利益計画、分析と検証は幹部によって重要な要素です。
数字に強い管理者を目指したいものです。
本日は外部講師に 山下久幸税理士事務所、代表の山下久幸氏に指導をしていただきました。
基本的な数字数字の読み方、重要な指標についてポイントを押えらることができました。
参加者からの質問は経営のレバレッジに集中していたような印象です。
売上の増減によって営業利益変化率が大きく変化することはリスクが高いこととなりますが、
製造業以外ではその指標を持っていないことも多いですね。
感覚的に固定費や変動費に振り分けていることは危険が伴うのです。
*経営レバレッジ係数(DOL)×売上高の増加率=営業利益増加率

「お客様の役」VS「営業マンの役」
営業マン・トレーニングでは2日間、実践的なロールプレイをし続けました。
ステップは4つ。
●訪問時の挨拶とアイスブレークで親しくなる
●ヒアリングでニーズを聞き出す
●顧客の立場で使用する自社商品のメリット提案
●次回の約束をするクロージング
相手のことを考える会話、あらかじめターゲットに合わせたセリフ想定、
説明ではなく顧客価値を伝えられるプレゼンテーション・・・
そのどれもが、じっくりと丁寧に向き合わなければならない成果のための準備なのです。
■企業内での研修では、独りよがりになりがちな営業活動、抜けている点や不足している点を
皆で観察とコメントし合うことで客観的に見つめられました。
自社商品の説明も、様々な伝え方があり、情報収集となります。
■実際の上司が役割として自社内で指導するOJTだけで不足しがちな基本的スキル、
態度スキル、会話スキル、客観的な視点、考え方と心構えなどを磨く能力開発の機会となります。
ロールプレイでは自社商品1点を実際に売る想定で行います。
皆が真剣に演じ、真剣に振り返り、真剣に計画を立てられる場となります。

管理職としての責任を問われているが、よく考えてみると、
“管理職としてのマネジメントスキルをきちんと学んだことはない”という人も多いのではないでしょうか?
良いマネジメントをするために基本知識を修得することは、本当に重要なのです。
今回の企業研修は、松田正幸講師の担当です。
管理職として部署の業績責任を持っていますが、どうしても目の前のコトに追われてしまう。
その根本的な問題は、組織全体を俯瞰していない、自分の人生全体を俯瞰していない、
楽な方向に目を向ける現状適応型の生き方をしていくうちに、本来の組織の目的と反する行動を
取ってしまう自分・・・に参加者は気づかされた1日でした。
とてもスピーディーで豊富な具体例の中に、危機感を求められる意識改革研修です。

研修スタートしました。
今回の担当は大人気の髙木菜穂講師です。
「本日の内容は良く分かっていて、できていると思う人?」と質問すると、
何とほぼ全員が手を挙げています。
「どのくらいできていますか?」の続けての質問には
6割~7割という返答。
かなりの自信が皆さんにおありのようでした。
さて、6時間の終日研修を終えて、再び皆さんの感想を聴きますと、
「できていると思っていたけど、できてないこと、わかっていないことがたくさんあった」
「こんなこと、考えたことがなかった」
「会社のこと、わかっていなかった」
「今まで、深く考えずに仕事していた」・・・・などなど。
全員に問いかけ、全員で考え、全員で返答していく、真の自己改革を求める1日でした。

現状よりももっとサービスを良くしたいという経営者の思いがあります。
しかし、スタッフは「できている」と思っています。
中途採用や経験者スタッフが多い場合ほど、社内のサービス基準が個人基準となり
ばらついています。
また、指導者(店長、マネージャーなど)自身ができていないことも往々にしてあります。
写真は、某企業様にて、5部門から集まったスタッフ研修です。
部門内も、部門間も不統一になりやすいのが問題でした。
なぜなら、業種、立地、価格帯、スタッフの経験年数や力量…などがバラバラ
しかも、会社創業の際に、経験者を集めてスタッフとして雇用したからです。
一度、ちゃんと消費者目線で確認しよう!とか、顧客の立場で再確認してみよう!、と
いう時には、当社のような教育専門会社にぜひ連絡してみましょう。
何をしなければならないか、早い時間で解決策が出るはずです。

訪問するよりもはるかに簡単だと言われているカウンター営業。
実は非常に難しいのです。
初めて会ったお客様を少しの会話で見極めて、その方に合った商品や
サービスをご提案することは、大変高いコミュニケーション・スキルを要求されます。
訪問型の方が、お客様情報を事前に収集しやすいので会話や提案商品を用意しやすいものです。
今回はカウンター営業のトレーニングを行いました。
挨拶からクロージングまでの一連のシナリオをつくることが大事です。
基本の台本とやるべきことを決めて、それを守ること。あとは応用。
会話技術は何度も練習して磨きます。
精度を高めるには計画、準備、そして練習が何でも大事です。
担当は深月敬子でした。