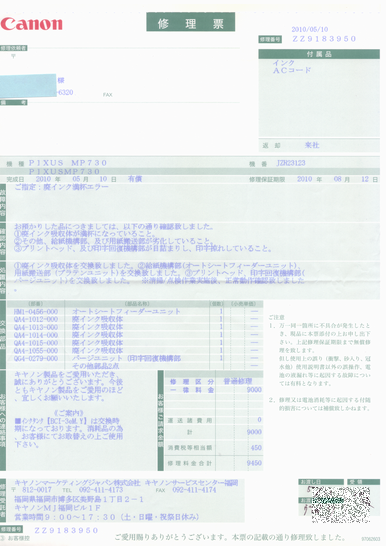最近、「一般職対象の教育」のご相談が増えています。
コース別人事制度を採用している企業、していない企業どちらもです。
一般職は定型業務を主にこなします。現状では人件費抑制のため、派遣社員や契約社員、あるいはアウトソーシングに取って替わられる存在になってきました。
さて、在職10年とか20年の一般職の事務職の社員が、「若い派遣社員に比べて能力が劣る」ケースも多く出てきているようです。
総合職ではないので転勤や昇格もなく、一般職ならばこのまま長く安泰でいられるという緊張感の無さが成長を拒んでいるようです。
当社では前線のリーダーやラインの社員、営業社員という生産的な能力開発を主に請け負っています。彼らは能力開発が特に求められるため、組織から教育機会を多く得られます。
また、自分がもっと向上したい、達成したいというモチベーションが元々高い人が多いです。
ただ、組織全体で目標達成していく一体化はどうしても必要です。営業マンだけが突出して前向きで、一般職間接部門が足を引っ張っていては全員での目標達成が妨げられます。
一般職も同様に、専門的な能力や、チーム協働意識を高める必要があるのです。
管理職はそのひと本人だけに問題があると思っているようです。
「だいたい最近のスタッフは・・・」と愚痴をこぼす方が多いようです。
さて、本人にしっかり気づきを与えることが必要です。当事者意識・問題意識をもっと認識させるところから始めましょう。期待される仕事をしていない、ことを明示しイエローカードを発するべきなのです。
それに加えて、管理職は真に彼らに『期待』をして欲しいです。具体的に、何を成果として求めるのか、言葉にして発信して欲しいです。彼らは、何を期待されているのかすら、まだ気づいていないのです。
外部研修に参加したから、すぐに問題意識が高まるとは言えないでしょう。職場での管理職が『彼らを持て余す』状態から一歩、抜け出して、本来の人材育成として人間的に接して欲しいと思います。
職場ぐるみ研修の実施も効果的です。目標管理制度の導入も必要です。