企業幹部としてのマネジメントを学ぶ3ヵ月6回講座が始まりました。
組織を引っ張るリーダーとして、自らの使命感を高め知識と技を磨く実践的講座。
内容は経営理念・組織管理・財務・人材育成等の内容。戦略性や問題解決力を高め、
ゼミ形式でのディスカッションで討議力を身につけます。
6回を通して自社課題を解決する力をつけます。

「お客様の役」VS「営業マンの役」
営業マン・トレーニングでは2日間、実践的なロールプレイをし続けました。
ステップは4つ。
●訪問時の挨拶とアイスブレークで親しくなる
●ヒアリングでニーズを聞き出す
●顧客の立場で使用する自社商品のメリット提案
●次回の約束をするクロージング
相手のことを考える会話、あらかじめターゲットに合わせたセリフ想定、
説明ではなく顧客価値を伝えられるプレゼンテーション・・・
そのどれもが、じっくりと丁寧に向き合わなければならない成果のための準備なのです。
■企業内での研修では、独りよがりになりがちな営業活動、抜けている点や不足している点を
皆で観察とコメントし合うことで客観的に見つめられました。
自社商品の説明も、様々な伝え方があり、情報収集となります。
■実際の上司が役割として自社内で指導するOJTだけで不足しがちな基本的スキル、
態度スキル、会話スキル、客観的な視点、考え方と心構えなどを磨く能力開発の機会となります。
ロールプレイでは自社商品1点を実際に売る想定で行います。
皆が真剣に演じ、真剣に振り返り、真剣に計画を立てられる場となります。

管理職としての責任を問われているが、よく考えてみると、
“管理職としてのマネジメントスキルをきちんと学んだことはない”という人も多いのではないでしょうか?
良いマネジメントをするために基本知識を修得することは、本当に重要なのです。
今回の企業研修は、松田正幸講師の担当です。
管理職として部署の業績責任を持っていますが、どうしても目の前のコトに追われてしまう。
その根本的な問題は、組織全体を俯瞰していない、自分の人生全体を俯瞰していない、
楽な方向に目を向ける現状適応型の生き方をしていくうちに、本来の組織の目的と反する行動を
取ってしまう自分・・・に参加者は気づかされた1日でした。
とてもスピーディーで豊富な具体例の中に、危機感を求められる意識改革研修です。

研修スタートしました。
今回の担当は大人気の髙木菜穂講師です。
「本日の内容は良く分かっていて、できていると思う人?」と質問すると、
何とほぼ全員が手を挙げています。
「どのくらいできていますか?」の続けての質問には
6割~7割という返答。
かなりの自信が皆さんにおありのようでした。
さて、6時間の終日研修を終えて、再び皆さんの感想を聴きますと、
「できていると思っていたけど、できてないこと、わかっていないことがたくさんあった」
「こんなこと、考えたことがなかった」
「会社のこと、わかっていなかった」
「今まで、深く考えずに仕事していた」・・・・などなど。
全員に問いかけ、全員で考え、全員で返答していく、真の自己改革を求める1日でした。

現状よりももっとサービスを良くしたいという経営者の思いがあります。
しかし、スタッフは「できている」と思っています。
中途採用や経験者スタッフが多い場合ほど、社内のサービス基準が個人基準となり
ばらついています。
また、指導者(店長、マネージャーなど)自身ができていないことも往々にしてあります。
写真は、某企業様にて、5部門から集まったスタッフ研修です。
部門内も、部門間も不統一になりやすいのが問題でした。
なぜなら、業種、立地、価格帯、スタッフの経験年数や力量…などがバラバラ
しかも、会社創業の際に、経験者を集めてスタッフとして雇用したからです。
一度、ちゃんと消費者目線で確認しよう!とか、顧客の立場で再確認してみよう!、と
いう時には、当社のような教育専門会社にぜひ連絡してみましょう。
何をしなければならないか、早い時間で解決策が出るはずです。

訪問するよりもはるかに簡単だと言われているカウンター営業。
実は非常に難しいのです。
初めて会ったお客様を少しの会話で見極めて、その方に合った商品や
サービスをご提案することは、大変高いコミュニケーション・スキルを要求されます。
訪問型の方が、お客様情報を事前に収集しやすいので会話や提案商品を用意しやすいものです。
今回はカウンター営業のトレーニングを行いました。
挨拶からクロージングまでの一連のシナリオをつくることが大事です。
基本の台本とやるべきことを決めて、それを守ること。あとは応用。
会話技術は何度も練習して磨きます。
精度を高めるには計画、準備、そして練習が何でも大事です。
担当は深月敬子でした。

「最近の若者はどうも問題が多い・・・」
「部下はやる気がない、指導したことを守らない」
「何を考えているかわからないからソッとして関わらないようにしている」・・・・
などなど、企業現場に行くと、管理職やリーダーが若い社員への指導や管理に悩んでいる声を
よく耳にします。
今回は、コーチングの手法を使ったリーダー研修です。
ペアワークなどで、話す聴く、承認する、質問する…などのスキルを磨きます。
まずは、相手を肯定することから始めましょう!、という木村千歳講師。
コミュニケーションの成果は「相手が決める」のです。
部下に合わせ、違いを認め、そして共存する。互いに認め合い、生かし合う。
命令の仕方や管理の仕方の技術ではなく、一緒に「船に乗るための」乗り方の
コツを修得できるものです。
皆さんのワークでは笑顔がこぼれ、「これなら明日からできそう」という感想をたくさんいただきました。
「グループのメンバーを変えてもらえませんか?」
「どうしても参加しないといけないんですか?」
「他の人とレベルが違うので、合わせられません」
「一人で学びたくて申し込んだのですがグループだといやです」
・・・など、このようなご意見をいただくことがあります。
非常によくわかります。
ある知識を習得したい、一定のスキルを体系立てて学びたいという目的が明確で
個人で申込みをした方には、そのような思いが特に強いと思います。
自分でも知識や経験がある方は、特に共感できると思います。
私が過去に参加した研修でも、この形式で非常にとまどい、うまくいかなかったことがありました。
メンバー全員がやる気がない方ばかりだった時です。
目的意識と背景が違う、多様な業種と職種の集まりであり、そして意見がバラバラで
まとめようと誰も思っていないので何も決まらず、困り果てたことがありました。
今、各種の研修ではほとんどグループでの活動を一部でも取り入れることが多いです。
座学だけでは学んだことが実際に発揮できない場合もあるため、実習して体で覚える、とか
数名で話し合う、ゲーム式で一緒に演習を解いてみて学んだことが納得できる参加型研修
…などが主流になっています。
特に有効なのは、社内研修です。
意識を統一したい時、情報交換の場にしたいとき、チームワークを醸成したい時、
創造的なアイデアを発散する場合には特に有効でしょう。
しかし、個人ワークが適切なときもありますので
何でもグループで行うというのは難しいでしょう。
所属する組織が違う集合研修、個人が集まっている研修ではグループに構成するときから
大変な気配りをすべきです。
目的に合わせ、一定の属性を基準にして同一カテゴリーで集めるのか、別カテゴリーに
するのか。個人の意思で申込みしたのかどうか、、
習得レベルで階層化するのか、自由なグループを選択できるのか・・・?など
グループの持つ意味と、ワークに求める成果を考えておかないと、
受講者の意欲が減退したり、まったく学習効果がなくなったりします。
グループに偏りが出た時こそ、これをどうやって研修内容とつなげて理解してもらうか、
講師のファシリテーション力として腕の見せ所です。
ただし、リーダー養成研修はグループをまとめる力を求めるので、グループワークは多用します。
先日のある研修会で、受講者から「グループはやめて」と申し出がありました。
その研修は、「リーダーとしてまとめる」能力を向上する研修でしたので、グループ活動は
減らさず、目的を伝えて参加していただくよう説得しました。
リーダーは、部下や構成メンバーを選べません。
目的に応じて、メンバーの力を引き出すことが求められます。
グループによっては、課題の意味を取り違えていたり、時間内に結論までいかなかったり
一人で何でも決めてしまう人がサッサとワークを終えてしまったり…する場合にも出くわします。
その場面は、職場にもよくある場面に似ています。
リーダーとして、何をすべきか。
このワークでの自分の立ち位置や発言、役割は適切だったのか、他人を否定だけして
傍観者でいただけではなかったか・・・、などのフィードバックが結構な気づきを生むものです。
他のグループと競い合うことで、非常に良いパフォーマンスが生まれることもあります。
参加者にとって、どういう形態が最も習得が早くて効果的なのか、
研修プランニングをする立場として熟慮すべきテーマです。
深月敬子
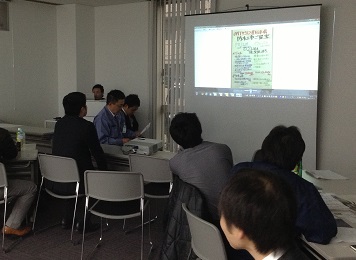
営業は体験が大事です。
理屈ばかり学んでも力がつきません。
しかし、実践の日々を続けても実績につながり続けるのは難しい。
いつの間にか我流になったり、間違っていたり、時代に合わないこともあります。
時々振り返って、方法や技術を加えたり、忘れていた基本を思い出したり、
戦略を練り直したり、新たな意識をもってやる気になったりするのが営業マン研修です。
こちらの研修では、基本に返った営業基礎スキル・商談話法だけでなく、
何と、現場で実際にあった商談例を持ってきて、実践的な事例として検討し、
提案力を磨く研修を行いました。
グループ4名程度で構成して、それぞれ別の商談事例を担当しました。
実際に顧客役のスタッフからインタビューによって情報を得るところからスタートします。
ヒアリングで得た顧客の真の問題から、自社独自の提案をまとめます。
グループでまとめる時間は約1時間。
その後、企画書を映写しながらのプレゼンです。
先ほどの顧客役のスタッフは、その提案に対して採否を下します。
提案の中身と価格、独自性、アフターサービスまで要求は高く、
本当に顧客が欲しいこと、実現したいことを伝えられているか判断します。
プレゼンテーターだけでなく、見ている他の参加者も真剣勝負の時間です。
グループがいくつかあると、このような実践型研修は、互いの学びとなるのでより効果的です。
聴く力、質問する力、商品の説明力、顧客との関係構築力、クロージング力・・・
多くのことが学べる実践研修です。
この研修は、定期的に行った6回目のまとめとして行いました。
最初から、実践編だけを行うのは難しいでしょう。
基本を学習して、実践力を高めたい組織には取り入れる価値があると思います。

コミュニケーションが求められる場面とはなんと多いのでしょうか?!
・管理職としての部下指導力、リーダシップを高めたい
・基礎的な報連相から、創造的な報告、緊急報告が的確になりたい
・取引先や外部との交渉や折衝力アップ。真のニーズをつかみ提案につなげたい
・あらゆる場面での新たな提案や問題提起をしたい
・信頼関係をつくるためのベーシックな態度スキルを上げたい
・具体的な行動指示、ほめる、叱る、質問する、気づかせる…テクニック
・社内の部署間連携を高めるための連絡、会議、ミーティングでの簡潔、迅速、的確さ
・営業職の新規開拓、得意先との関係づくり ・・・
組織間の連携を深めるためにも、個人のコミュニケーションは友好的で創造的なものが
望まれます。
単なる対人スキルとしてよりも、もっと問題解決能力を高める研修が効果的です。
最近の研修では組織丸ごと研修、具体的な事例研修などのご要望が多いようです。
写真は福岡市内の某企業様の研修。休日返上で1日6時間コース、ワーク型研修です。
グループで活気ある演習の中にもしっかりと各自の強みや弱みを認識し、
組織に活かせる課題や、個人がレベルアップしたいテーマを明確にできました。
≪感想より≫
・コミュニケーションの重要性を再認識できた
・今まで何となくやっていたことが体系立てて理解できた。今まで相互理解できていなかったと反省した
・論理的に組み合わせて伝えることの重要性がわかった。
・話し方、表現の仕方、組み立て方、聴き方を総合的に理解できた
・打合せ、報告書、説明、社内の連絡などに活かしていきたい
・多岐にわたった興味深く意義ある研修だった
・体験するワーク式研修だったので実際にやってみることができた・・・・