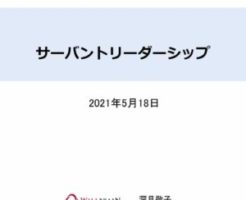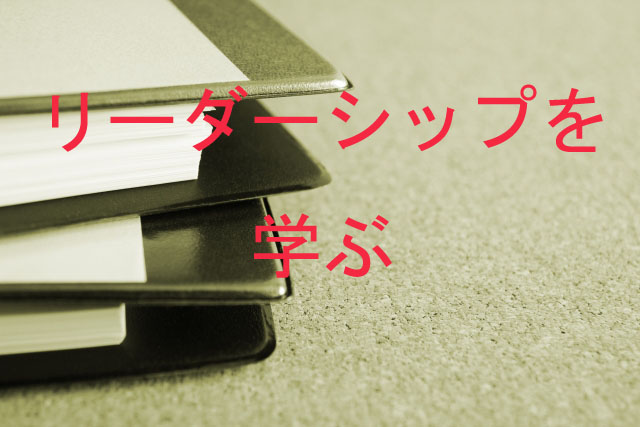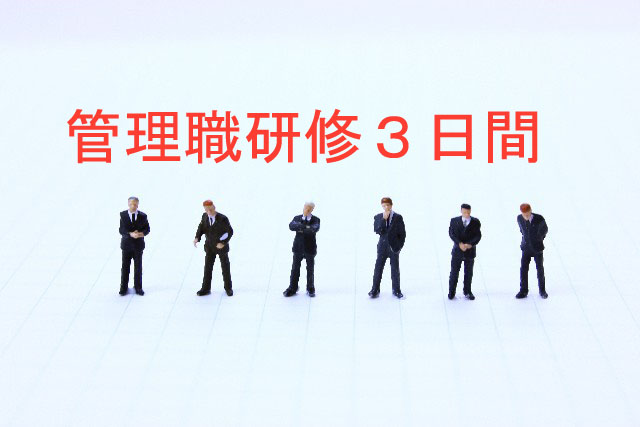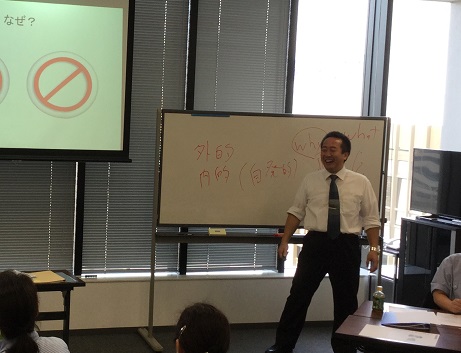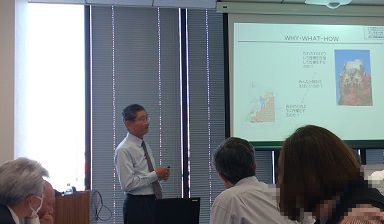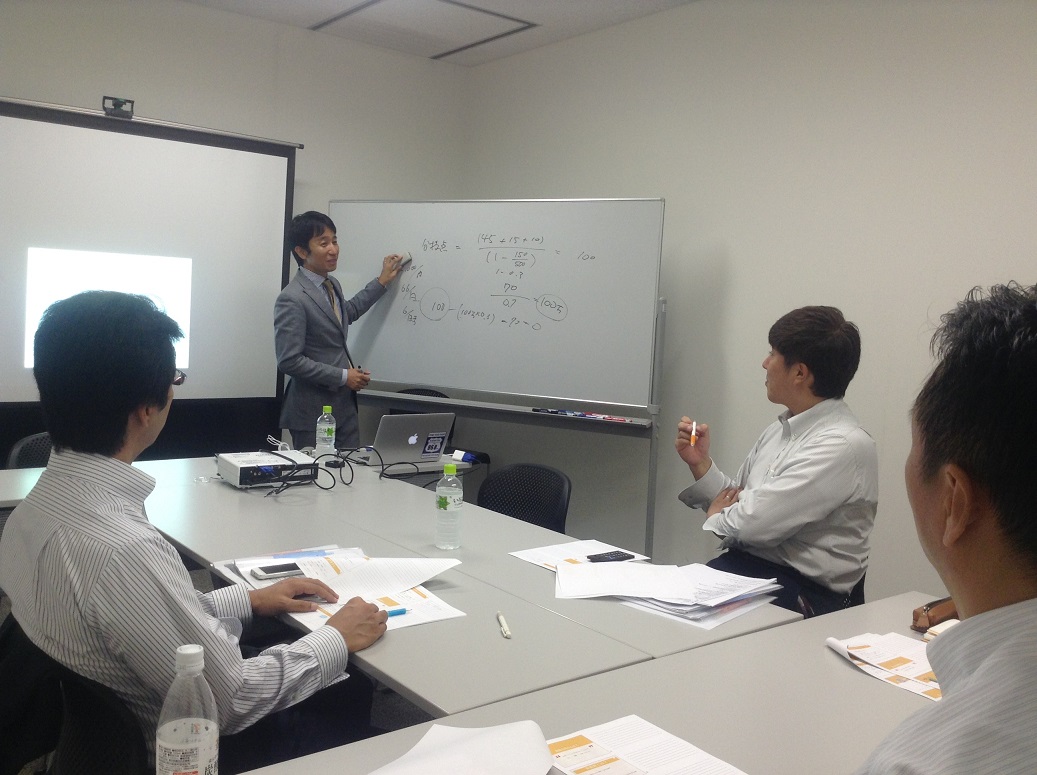「サーバントリーダーシップ」について講演をさせていただきました。
「北西会」(一般社団法人北九州青年経営者会議)の定例会にて5月18日講師としてご招待いただきました。
北西会とは、北九州市内の経営者の団体で20歳から40歳までの会員がリーダーシップをもって、
社会への奉仕などさまざまな活動や企画を通して、北九州の明るい未来を創造し活動なさっています。
5月の会で、今、注目されている「サーバントリーダーシップ」を学びたいというお話で、
出向いてお話する予定でしたが、緊急事態宣言下となりオンライン講演となってしまいました。
画面上であっても、若々しい会員の皆様はとても熱心に聴講いただきました。
※下記、会のホームページにもご紹介いただいております。
https://hokuseikai.com/archives/751/
“サーバントリーダーシップ”とは、メンバーへの奉仕・支援を通じて組織を動かすという考え方です。
ミッションのもとに判断し、ミッションへまず自ら行動します。
ただ部下の機嫌をとったり褒めたり奉仕する…という行動をさすのではありません。
部下に命令して仕事を進めるのではなく、どうすれば部下の持つ能力を最大限に発揮できるのかを考え、
それが実現できる環境づくりや部下への支援を通じて仕事を進めることから、この名がつけられました。
傾聴,共感,説得,概念化,先見などのヒューマンスキルが必要とされます。
実は、支配したり、威圧感を与えたり、権限を持って命令する方が、手っ取り早いのです。
ムチや大声、暴力…強い者に従わせるやり方。
でも、一時的に従っても世界は良くならず、暴力は連鎖していくものです。
恐怖によって従わされた部下は、仕事に本気で向かわず、上司のいない場では力を抜き、評価だけを気にするようになります。
心からリーダーに従わず、いつもビクビクしています。
意思決定を自分でしない部下は、いつの間にかどっぷりと依存していきます。
部下は本当の事を言わず、主体的にも動かず、指示だけを待ち、幸福感がない。やる気なく不幸なのです。
上司は、いつも意思決定を自分で行い、判断に迫られる。・・予測できない世の中、これもなかなかきついです。
相手が主体的に動くために、「命令しない」「大事なことに気づかせる」のは時間がかかります。待つ時間が必要です。
理念(ミッション)にそって深く問いかけ、横に並んで自分の姿を見せ、一緒にやる意義を
伝え続け、励まし、あきらめずに進むこと。
一人ひとりが違う情報をもち、違う強みを持っているので、それを合わせて行けばよい世界が作れるはず。
誠意、正直、献身、敬虔、謙虚、崇高…高い精神性があり、そして行動力が備わっているリーダーへ。
誰をも傷つけず、世界をよくするために発信し、互いに協力できる行動が起こせること。
勝ち負けや物質的な充足、妬みや恨み、怒り、欲望や恐怖、プライドで人生が満たすのではなく、
精神的な充足、慈愛、気高さ、奉仕、利他、といったエネルギーであるパワーで生きること…。
私の周りにも世界中にも、まだまだ威圧的な方々が多いのです。男だけでなく女も。
感情が高ぶって怒鳴るのは関係が近いほど(家族や部下など)、その人へ矛先が向います。
権力が欲しくて優位な資格をとる、受験勉強する、権威者に媚びる…なども多数。
組織で役職を目指す理由は、すなわち権限が手に入ると思っていらっしゃるのです。
元々、被害者だったからこそ、その力が欲しいのです。それを終わらせることを選んで欲しいです。
ガンジー、キング牧師、マザーテレサ…など歴史上のサーバントリーダーは暴力や権限を使わず、
ミッションのために非暴力を徹底しました。
たとえ自分が暴力を受けても絶対に「やり返さない」こと。暴力を返報しないこと。
精神的なその導きは世界中の人に今も影響を与えています。
今回は、そんな偉人たちの動画も見ていただきながらお話しました。
競争の中にいると、目に見える物質的で即効的な目標に向かいがちですが、
哲学定なベースとして「Do」ではなく「Be」の自分の在り方を問う機会があると良いと思います。
研修会などで皆様と一緒に話し合ってみたいですね。
※サーバントリーダーシップ研修・リーダー研修に関する詳細はこちら